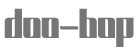【OUTIL】フランスに魅せられて
「僕にとってOUTILというブランドは、人と人とを繋ぐツールなんです」
今シーズンより取り扱いを始めたブランド『OUTIL』。
古いフランスのワークウェアからインスパイアされたコレクションの数々。
デザイナーである宇多 悠也 氏に、フランスという国の魅力、
そして洋服をつくるときに大切にしていることをお伺いしました。

中島:まずはそうですね、なぜそこまでフランスに魅了されたのか、のめり込んだのか。
フランスのここが面白いからやめられないっていうのがあれば教えていただけますか。
宇多:フランスの魅力、そうですね。
具体的に「これ」っていうよりは、ぼんやりと好きだなっていう感じですかね。
例えば外国、あるいは日本のどこか地方に行ったとき、
それぞれの場所の空気、雰囲気が自分に合う合わないっていうのがあると思うんです。
なんとなく、「なんか好きだな」、または「違うな」って。
それは例えば、車で移動しているときに見える自然の風景であるとか、
そこで出会った人たちの表情であるとか。
僕にとって外国でいうと、アメリカのニューヨークなんかも初めて行ったときには良いなと思ったんです。
当時は若かくて、そこには刺激がたっぷりとあったから。
でも実際に仕事ではなくプライベートで外国に行くタイミングがあったとき、
なぜかいつも自然とフランスを選んでいたんです。
たぶんこの国のなにかに引っかかったんでしょうね。
その当時は今と違って、黄色人種というだけで差別を受けるようなこともあったんですけど。
例えばレストランではメニューすら貰えないとかも多々ありましたね。
それでも日本に帰るときには、「また来たいな」って。
中島:フランスという国の空気がしっくりときたんやね。
それでもうフランス行き始めて何年くらいになるんですか?
宇多:初めて仕事で行ったのは、自分が22、3歳のときですね。
なので仕事で行くようになってもう15、6年になりますか。
フランスの地方にまで行くようになったのは、買い付けの仕事がきっかけだったんですよ。
ヴィンテージの洋服やアンティークの什器などを探しに、アンティークの家具屋さんと一緒に回っていました。
南フランスにも行くようになり、色んなヴィンテージディーラーに会っては買い付けをしていましたね。
そうこうしているうちに、だんだんとヴィンテージの数も減ってきて、
欲しいものが欲しい値段で買えなくなってきたんですよね。
それで僕は元々モノづくりもしていたので、だとしたらこの国でなにか作れないかなと。
まだ生産できる場所が残っているのだから、それをしたいなって。
じゃあ実際にそうするにはどうするのが良いかと考えるようになって、
なら工場に行ってみようというところから始まったんです。
結果そこから今に繋がっているのかなと思います。
けど難しいですね。
フランスの魅力、全部「空気」とか「雰囲気」っていう曖昧な表現になってしまって。
それでも確かにそれは存在すると感じていて、やめられないなと。

中島:ご自身でもそれが何なのかは、現状まだ模索中という感じですか。
宇多:そうなんですかね。
ああ、でも明らかに他の国とは違うものって考えると、
「色」っていうのに関しては、感じ方とか出し方は絶対に違いますね。
例えば同じインディゴであっても、アフリカやインドで見るインディゴと、
フランスのインディゴでは青の青味っていうか、明らかに違うなって。
これは僕がよく思うことなんですけど、
フランスの南の方で、夏の夜、9時半とか10時にかけて空がだんだんと暗くなってくるんですよね。
そうやって暗くなってきたときに、空の青がどんどんネイビーになっていく、
黒になっていくっていうその中間に、「すごく良い色」みたいなのが存在して。
それが自分の中ではすごく大切で。「ああ、この色だ」っていうのがフッとくるんです。
それをなんとか形にして、人に伝えたいってなったとき、
フランスでやるからこそ上手くいくっていうのはあると思います。
中島:なるほどなあ、確かにフランス、ヨーロッパの色って独特のものがあるよね。
あ、フランスの服のここが面白いみたいなのもあれば教えてもらっていい?
宇多:僕が好きなフランスのワークウェアは1940年代以前のもので、
特に30年代と40年代のものに関して、ピンポイントですごく好きなんですよ。
その時代のものには自分が思う「エレガンス」があって、それがフランスの服が好きな理由です。
その時代にはモールスキンみたいな厚くて丈夫な生地を、
今見ると正直合ってない方法で縫製しているんですけど、なんかそこが良いよねっていう。
より効果的、効率的な縫製をまだ思いついてなくて、
でもだからこそ無駄なパッカリングとかも生まれずに「綺麗だな」って。
当時の服にはちょっと女性的な部分も感じて、ああ良いなって思えるんですよね。
そういうのはその時代のフランスの洋服にだけ感じる魅力で、シルエットとかもそうですし。
例えば丸すぎる襟とかは分量も悪いし、生地の取り分を考えたらコストもかかるんですけど、
でもこれが当時のフランスだなっていう。
そいった凄く小さいところなんですけど、でも当時のフランスだからこそあり得たディティールに強く惹かれるんです。

中島:この春からOUTILの洋服を取り扱わせていただいているんですけど、
宇多さんが作らはるものってなんかこう、中々理解が難しいんですよね、正直言うと。
大体のデザイナーにはここが好き、大事なんやろうなっていう、その人の芯というか指針が見えるんですけど、
宇多さんにはまだぼんやりとしか見えないんですよ。僕自身は。
なので改めてお尋ねしたいんですけど、宇多さんがモノを作るときに1番大事にしているものってなんでしょう。
全てって言ってしまうことも出来るとは思うんですけど、さっきの話聴いた感じやと「色」?
宇多:そうですね、やっぱり色かな。あとはタッチ、生地の触感ですね。
もちろんパターンとかも大事だとは思うんですけど。
けどなんですかね、それと同じくらい「ふわっと何がしたいのか」を大事にしています。
例えばここ最近では、自分が興味あるもの、何が今いいなと思っているのかと考えたときに、
「左右のバランスが悪いもの」っていうのに惹かれていて、ならそれを表現しようって。
中島:あ、今回のアシンメトリーのパンツですね。
宇多:今シーズンだとそうですね。以前のシーズンではシャツやジャケットでも作っています。
その「何がしたいか」を、自分のキャパシティの中でどう表現できるかっていうのが
たぶん最初にポイントになってます。
最初の発想、自分が今興味あるのはそこだっていうのを大切にしていますね。
色に関しては、シーズン毎になんとなく自分の中で決まっています。
始めの時点で今回はこの色だなっていうのが1色か2色は絶対決まっていて、
あとはそれに対しての調和というように考えているので。
例えば今シーズンでいうと「ピンク」というものが浮かんで、それに対して周りをどうするのかっていう。
もちろん、それ以外のものは手を抜いているということではないんですけどね。
だから順番でいうと、「色」があって、「ふわっとやりたいこと」があって。
それに対して生地をどうするかといった具合ですかね。

中島:なるほどね、色と興味があること、やりたいことか。
今回春夏でピックアップしたアシメのパンツに関しては、
本藍と木炭を混ぜてあの色味を出しているんですか?
これどうやって染めてるんやろって思って。
宇多:あの色はですね、インディゴで1回染めたあと、スミでもう1回染めているんです。
絵具を使ってキャンバスに色を重ねていく様なイメージですね。
水彩画とかで、絵具が混ざりきっていないところのムラが綺麗だなって感じることがあるんですけど、
あの色はその感覚で出していますね。
僕がここだって思うニュアンスの部分、青からグレーに移行する途中の部分が欲しいっていう。
その色はどうやったら作れるのかなっていうのを、職人の方と話し合って試行錯誤するんですけど、
ニュアンス的な問題なので伝わる人とそうでない人がいるんですよね。
人から見たら青、別の人から見たらグレー。でも僕からしたらどちらでもないよっていう。
ただ自分にとってこの色だっていうのがきちんと出ていればそれでいいので、
なので表記上は「インディゴ」と「ブラック」ってさせていただいているんですけどね。
どちらも同じ生地で、同じ染めるものを使ってやっているんですけど、配分とか時間で差を出している感じです。
同じものを使ってもこれだけ違うんだっていうのを伝えたいんですよ。
中島:確かにあのパンツのグレーの中には青味があるわ。
あんな絶妙な色を初めから狙って出しているんか、凄いな。
宇田:大体の場合はそうですね。
そこが自分にとってとても大切な部分なので。
中島:あと生地にしてもえげつないの使ったりしてるよね。
次の秋冬でやらせてもらうパンツに使われてるモールスキンとか。
あれは織るにしても縫うにしても、どうしてんのかなっていうレベルやもんね。
宇多:あれは糸からすべてオリジナルの生地で、
おそらく他社では誰も出来ないと思っています。
あの生地の背景としては、やはりフランスのモールスキンになるんですけど、
実はフランスのモールスキンって30年代のものはまだ薄いんですよ。
それが40年代になると厚みが出るんです。でもしなる、嫌な硬さのない柔らかい生地で。
見てもらったパンツの素材っていうのは、まさにその40年代の生地を目指して作ったものなんです。
この生地を作るのに、僕が持っているヴィンテージのジャケットの生地を工場の人に見てもらってたんですけど、
どこに行っても織れないって言うんですよ、ここまで打ち込むことなんて出来ないって。
というのもすごく細い糸を使って、限界を超えた打ち込みをしてあったんですよね。
当時は機械の限界なんて考えていなかったし、またそれを操れる技師がいたので。
でも「今」それをやりたいっていう強い想いがあって。
それで諦めずに、本当に色んなところを探し回った結果、形にすることができた生地なんです。
中島:そこまでの生地やったんか。
やっぱ違うよね、のめり込み方が半端じゃないっていうか。
でもほんとに宇多さんみたいな、そんなデザイナーの人たちとやっていきたいんよね。
本日はありがとうございました、これからもお願いします。
宇多:こちらこそ、よろしくお願いします。